


論理の変遷と社会的背景の呼応【第3回】(論理の変遷)
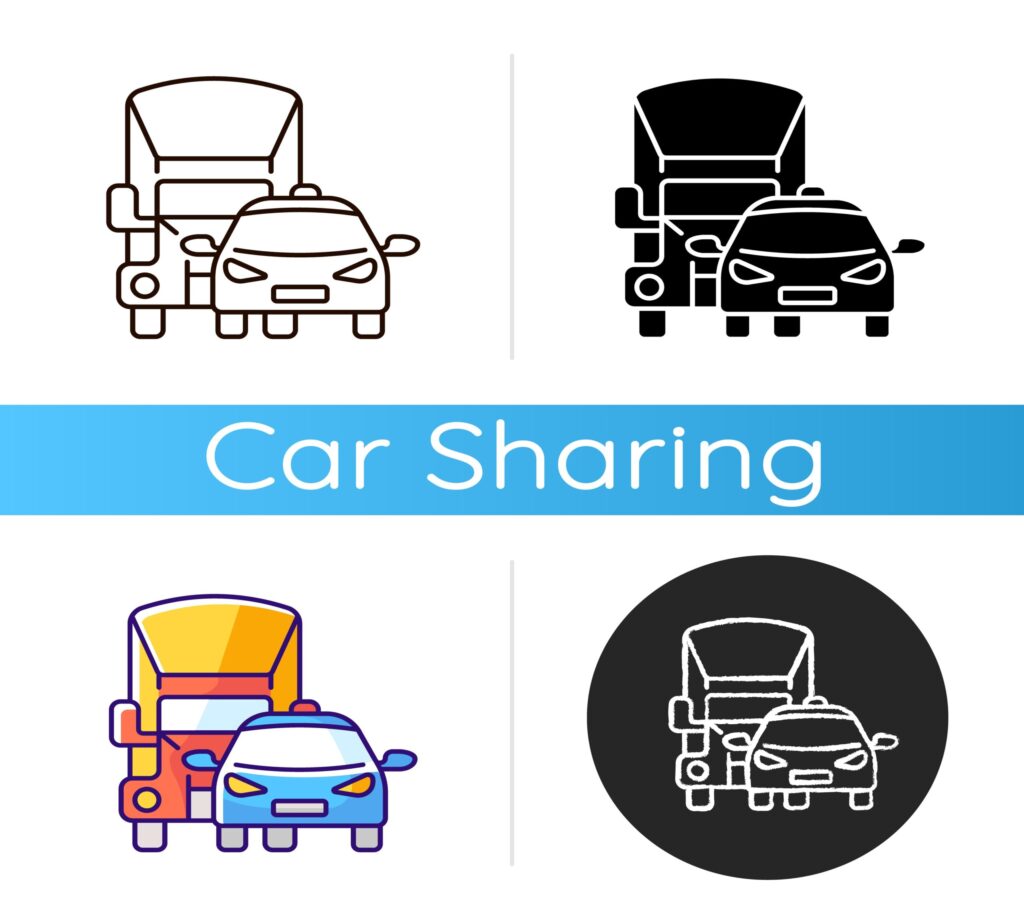
論理の変遷と社会的背景の呼応【第2回】(ドライブクラブとの比較)


前ページでは、制度の構造とその変遷を問いながら整理しました。
今回は、その問いを実際の判例に当てはめて、制度の抽象化が何を見落としたのかを読み解いていきます。
控訴審・最高裁ともに「Yは直接取り戻す方法がなく、任意の返還に期待するしかなかった」と述べていますが、その前提として警察への届出という選択肢がなぜ検討・実行されなかったのかは、判旨にも原審にも明示されていません。
この沈黙は、以下のような問いを誘発します:
| 観点 | 原審(地裁) | 控訴審・最高裁 |
| Yの対応 | 「被害届を出すと言えば返還された可能性あり」→責任肯定 | 「直接取り戻す方法がない」→責任否定 |
| 警察届出の扱い | 積極的に言及(しなかったことが問題) | 言及なし(スルー) |
| 黙認性の評価 | 使用継続を黙認したと評価 | 任意返還に期待しただけと評価 |
→ 控訴審・最高裁は、Yの消極性を「黙認」とは評価せず、「制御不能状態」として処理しているが、その過程で警察届出という制御手段の不行使を論理から外している。
事故が起きた“後”ではなく、“前”に―――
Yには、事故を未然に防ぐための警察届出という選択肢が、明確に存在していたはずです。
しかも、Aが「盗んだ車で事故を起こして少年院に送致された過去がある」ことをYは知っていた。
それでも警察に届けなかった。
この「届けなかった理由」が判決文に現れないのは、まさに構造的な問いの空白です。
法的な責任論ではなく、社会的・心理的な構造の読みとしてこんな問いが立ち上がる。
つまり、Yは「返してほしい」と言いながら、本気で取り戻す行動(警察届出)を取らなかった。
これは、制御可能性を放棄した責任が問われて然るべきです。
しかし、控訴審はその警察届出の「不在」をスルーして、欺罔(だましとられた)・制御不能(Aの行動を抑えられない)というフレームにすり替えました。
なぜ、裁判所はこの「不在」を見て見ぬふりをしたのか?
制度の予測可能性を守るために、問の誠実さが切り捨てられたのではないか?
次回は、その構造を解き明かす仮説を展開していきます。