


論理の変遷と社会的背景の呼応【第3回】(論理の変遷)
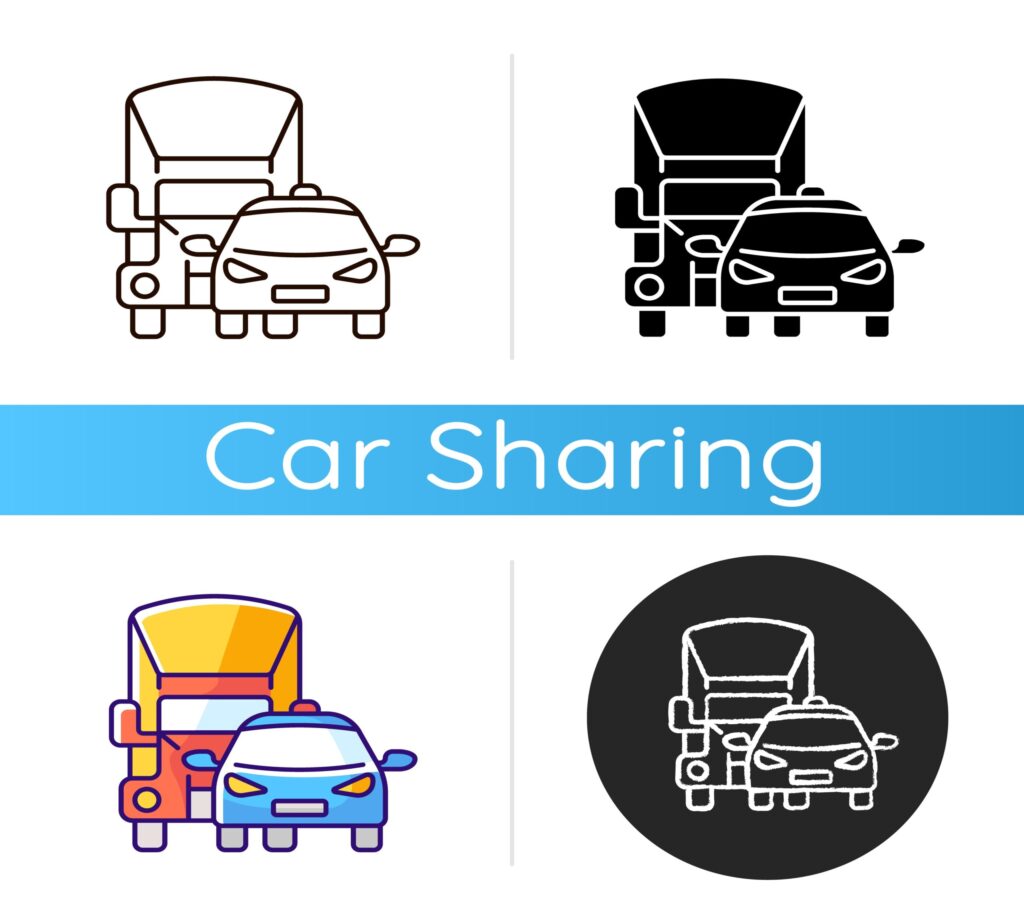
論理の変遷と社会的背景の呼応【第2回】(ドライブクラブとの比較)

Aさんは養老生命共済に加入し、災害死亡時に共済金が支払われる特約を付けていた。
夜、Aさんの車が道路右側に駐車されていたレッカー車に衝突。Aさんは頭部を強打して亡くなった。
事故後の検査で、Aさんの血液には1mlあたり0.98mgのアルコールが残っていた。
さらに、屈曲した制限速度40km/hの道を70km/h以上で走行しており、前方注視義務を怠っていたとされる。
争点は、こうした事故が「重大な過失」に当たり、共済金が支払われないかどうかであった。
最高裁は、血中アルコール0.98mgでも「かなり酩酊」と評価している。
しかし、血中アルコール濃度は0.98mg/mlと“軽酔”未満であり、判例の評価と医学的基準とは乖離がある可能性がある。
以下の表を参照してほしい。
| 酔いの段階 | 血中濃度の目安(mg/ml) | 状態の特徴 |
| 爽快期 | 0.2~0.4 | 陽気・開放的 |
| ほろ酔い期 | 0.5~0.8 | 判断力低下・多弁 |
| 酩酊初期 | 0.9~1.5 | 運動障害・感情不安定 |
| 酩酊極期 | 1.6~2.5 | ふらつき・嘔吐・記憶障害 |
| 泥酔期 | 2.6~3.5 | 意識混濁・失禁 |
| 昏睡期 | 3.6以上 | 意識喪失・死の危険 |
→0.98mg/mlは「酩酊初期」に該当する可能性はあるが、「かなり酩酊」と判断するには医学的にはやや弱い根拠である。
・酒気帯び運転:血中濃度0.3mg/ml以上(呼気0.15mg/L以上)
・酒酔い運転:濃度に関係なく「正常な運転ができない状態」
→ 0.98mg/mlは酒気帯び運転の基準を大きく超えているが、酒酔い運転かどうかは挙動・症状の観察が必要。
判例は、「制限速度40キロメートルの屈曲した路上を前方注視義務を怠ったまま漫然時速70キロメートル以上の高速度で運転をして」いたことを「極めて悪質重大な法令違背及び無謀操縦」としている。
アルコールのことを別個で考えると極めて不自然な説明ではないだろうか?
もちろん、制限速度を超える運転は本来望ましくないが、現実には40km制限の道路を70kmで走ることもあるだろう。読者の中にも、心当たりがある方はいるかもしれない。
また、屈曲したというのもどの程度の屈曲かは不明。
多少の屈曲であれば、70kmで走行したとしても「極めて悪質重大な法令違背及び無謀操縦」とまでいえるだろうか?
これは、“酩酊ありき”で他の要素を積み上げることで、結論を成立させていると考えられるのである。これが、判例のトリック1点目だ。
判例は、Aが「折から路上右寄りに駐車中の本件レッカー車に衝突」したとしているが、これに関して判例ではほとんど触れられていない。つまり、判旨ではその駐車自体が事故原因として問題になったとはされていない。
ただ、以下の点、問題がなかったと断定するには、慎重な検討が必要ではないか。
・レッカー車は「道路右側に駐車中」。
・衝突したのは「左側後部クレーン用側方アーム角部」。
→ 駐車位置・形状・視認性・灯火義務などに問題があった可能性は否定できない。
・判旨は一貫して「Aの飲酒・速度・漫然運転」に焦点。
・レッカー車側の過失や違法性には一切言及なし。
1. 制度的方向性との整合
・ 飲酒運転=社会的非難の対象。
→ 「酒を飲んで運転した者が悪い」という物語を壊したくない。
・ レッカー車の過失を認めれば、免責条項の適用が揺らぐ。
2. 保険契約の構造
・ 本件は「被共済者の重大な過失による災害か否か」が争点。
→ 第三者の過失は、免責条項の適用判断には“関係ない”とされる構造。
・つまり、裁判所は「契約構造に従って語る」ことで、論点を限定している。
3. 判例の語り方の美学
・ 判例は「語ること」と「語らないこと」の選択によって、制度の骨格を守る。
・ レッカー車の過失を語れば、「重大な過失」の物語が崩れる。
→ 沈黙は制度防衛の技法。
沈黙は制度の盾である。語られなかったレッカー車の過失は、免責条項の純度を守るために排除されたのであろう。
こちらも、最高裁は「酩酊+無謀運転」を前提にして結論を出している。これが、判例のトリック2点目。
レッカー車の駐車が少し危険でも、酩酊ありきの論理に隠れて問題視されていない。
「一見問題となりそうな事実も、論理構造によって無視されることがある。」
ここまで見てきたように、「かなり酩酊」という言葉は、制度的結論を支えるための語りの支柱だった。
だが、判例の語りにはもうひとつ、見過ごせない揺れがある。
それは、事故の相手車両の呼称──「クレーン車」と「レッカー車」の混在である。
一見すると些細な違いに見えるかもしれない。
しかしこの呼称の選択は、事故の印象、責任の構造、そして制度の語りの純度に深く関わっている。
なぜ判例は「クレーン車」と記しながら、判旨では「レッカー車」と語ったのか?
その語りの揺れにこそ、制度の沈黙と操作の技法が潜んでいる。
次の記事では、この「呼称の混在」に焦点を当て、判例が語るものと語らないものの境界線をさらに深く掘り下げていく。