


論理の変遷と社会的背景の呼応【第3回】(論理の変遷)
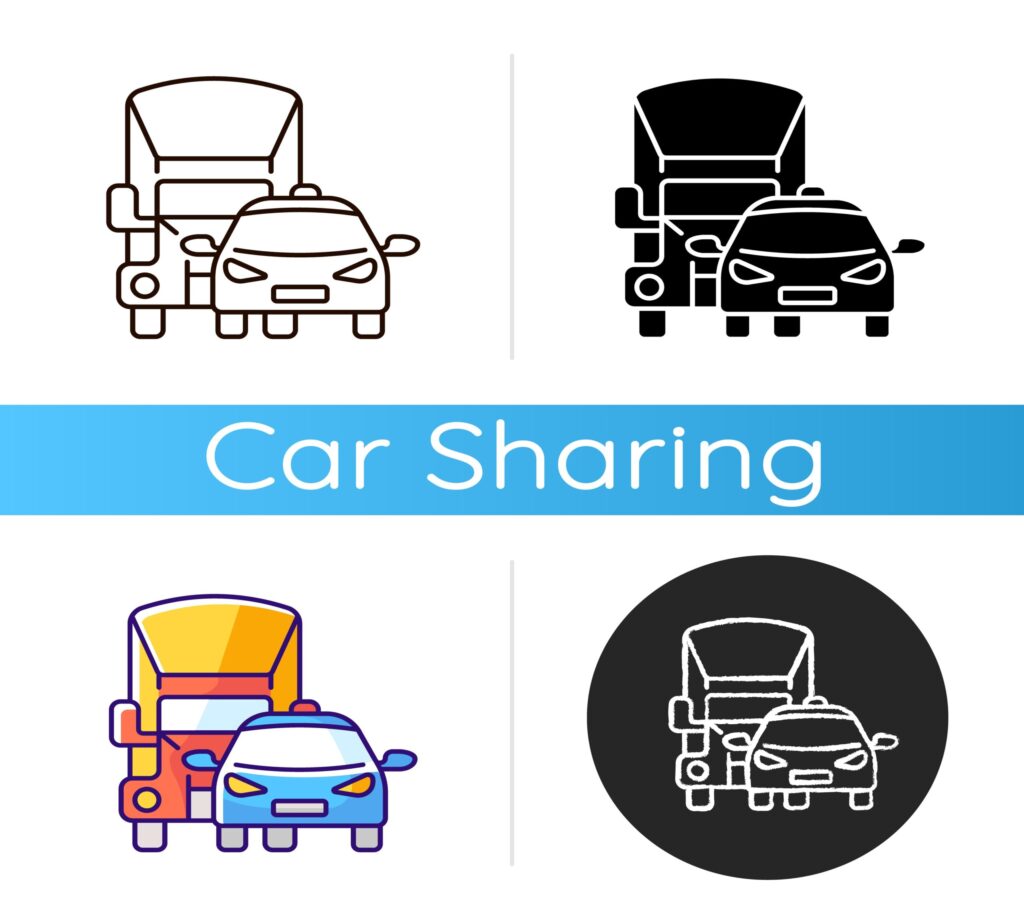
論理の変遷と社会的背景の呼応【第2回】(ドライブクラブとの比較)


前回では、裁判所は警察届出の「不在」を「欺罔」、「制御不能」という抽象ロジックにすり替え、制度の予測可能性を守るために、問の誠実さが切り捨てられた可能性について述べました。これについての私の仮説を展開していくのがこの頁です。
ここから私の仮説を2段階で考えていきます。
まず、1段階目としていえるのは、裁判所は、Yを運行供用者責任から切り離したかったから上記の抽象ロジックにすり替えを行ったということです。
なぜ、Yを運行供用者責任から切り離したかったのでしょうか?
以下4点があげられるかと考えます。
このように、控訴審は個別の事実評価よりも、制度全体の均衡と予測可能性を優先したのはなぜだったのでしょうか?
それは、制度の骨格を守るために、誠実さを“構造的に切り捨てる”必要があったからかもしれません。
高裁や最高裁は、単に事実を評価するだけでなく、法体系の整合性と制度の安定性を担保する役割を持っています。
そのため、以下のようなバランスを常に意識しています:
| 観点 | 地裁・原審 | 高裁・控訴審 |
| 重視するもの | 個別具体的な事実と行動 | 法的枠組みの整合性と制度の限界 |
| 被害者救済 | 積極的に評価 | 制度的責任の限界を意識 |
| 運行支配の評価 | 実質的・行動ベース | 抽象的・状態ベース(欺罔・断絶) |
| 判例との整合性 | 柔軟に解釈 | 過去の判例との一貫性を重視 |
このように、控訴審は「この事例で責任を認めてしまうと、今後どこまで責任が広がるか分からない」という制度的リスクを感じていた可能性があります。
今回については、本記事のタイトルにもあるように、制度の予測可能性を守るために、警察届け出の怠慢は免責されていいのでしょうか?
これは、いいかえると、
裁判は本来「個別具体的な事実に誠実に向き合う場」であるはずなのに、控訴審は制度の均衡を守るために、その誠実さを犠牲にした。
そしてその結果、人間が社会生活の中で果たすべき責任が、法的構造の中で免責されてしまった。
といえる。
人間が社会生活の中で果たすべき責任を免責してまで、裁判所が守りたかったものは何か?
制度の予測可能性の“さらに奥”に、別の構造的な答えが眠っている──
それが、私の仮説の第2段階です。続きは次頁に譲ることとします。